ページ目次
英語で「解凍できない」と言うつもりが
「ジッパーがうまく下がらないかもしれせん」
かつての職場での話。技術サポートの現場で、私の働いていた会社の担当者から、あるパートナー企業に、システムログのファイルを zip 形式に圧縮してお送りしました。
そのパートナー企業は、社員のほぼ全員が日本人の、日本企業です。一方、当時私が勤務していた会社は外資で、弊社側の担当者が日本人であったとしても、原則、全てが英語でやりとりされていました。
パートナー企業の日本人技術者から、以下のような英文がメールで送られてきました。
I tried unzipped the file.
But I could not be unzipped successfully.
まず、前半は、受動態の てい をなしていません。したがって、まともな英語の文章になっていません。
そして、この英文の後半は、
「(いまジッパーが生地を噛み込んでしまっているので)、自分の(ズボンの)ジッパーがうまく下がらないかもしれません」
と言っています……。
笑いごとではありません。問題は、
なぜこのような変なことになってしまうのか?
です。
実は、このたった二つの文章に、日本人英語に典型的な、かつ、致命的なミスが、つめ込まれています。
1. 受動態を使用しようとして失敗×2(アメリカ人の英語文章研究の泰斗 William Strunk Jr. は、「受動態を使うな」と言っています。)
2. 時制の表現のミス(この文章をネイティヴがパッと見たとき、could を can の過去形としては、まず解釈しません。)
そして、1. は、実は英語のミスではないと思います。「誰が、どうする、何を」という 2W1H に関して、日本語の段階で発話者の頭がごちゃごちゃしているのが、いちばんの原因です。そこさえはっきりしていれば、こんな間違いはしでかしようがありません。
この日本人は、こう書くべきでした。
I tried to unzip the file.(私が、解凍しようとした、そのファイルを)
However, I was not able to unzip it.(私は、解凍できなかった、そのファイルを)
ちなみに、この例文に関連して、日本人が間違えやすいミスをもう一つ指摘しておきます。
上記のケースで、弊社側の担当者がファイルを圧縮し直し、再度送付した結果、今度はうまく解凍できた開けたとします。
先方の担当者が下記のような英文を送ってきたら、どれも意味が意図とズレます。
各例文の後に書いた日本語は、ニュアンスを含めた、額面どおりの和訳です。
I could unzip it successfully.
→まだ試していませんが、今度はたぶん解凍できると思います。
I unzipped it successfully.
→かつてはそのファイルを解凍できました、今はやってみないとわかりません。
日本人の方がよくメールに書く I understood. は、
「かつてはあなたのことを理解できた、今はよくわからない」
といっているのです。
……ご存じでしたか?
ではどう書けばいいのか?このブログの中で、時制の書き方のパートで取り上げていきます。
日本人ビジネス英語のあるある
(IT技術の知識が多少必要です)
日本人のビジネス英語にありがちなミスをもう一つ取り上げ、他山の石としましょう。
ヨーロッパ在住のエンジニアと協業で行っていたソフトウェア開発の現場で私が目にしたメールの中に、下のような英文がありました。ある、ビジネス英語ができると自認している日本人の若いプログラマが、外国人エンジニア宛に送信したメールです。
(1) This API can use when memory free.
彼は日本では一流とされる国立大学の工学部を大学院まで卒業しており、海外でホームステイした経験もありました。
本人の言いたかったことはどうやら、以下のようです。
(1)’ メモリを解放するときはこの API が使える。
(注:上記の例文は、実際にそのエンジニアが書いた文章から、文法ミスの構造を損なうことなく、コンフィデンシャルな情報を削除、単純化したものです。)
短いのに文法的なミスを満載しているこの英文は、残念ながらこれだけでは意味が伝わりません。それどころか、このAPIが「メモリフリー」の際に何かリソースなり変数なりを利用できると(文法的には しごく もっともの)「誤解」される恐れは、大いにあります。
そもそも、他動詞 use がでてくるからには、「何を」使うのか、つまり目的語が必ずあるはずですが、この文にはありません。文型が文型として成り立つ条件を満たしていないということは、根本的に英文になっていないということです。本来は最後に来るべき「このAPI」が最初に出てきてしまった間違いを、彼は書き終わった後も修正できなかったようです。これは、単に能動態・受動態がマスターできていないということ以上に、
「主語(主体、subject)は何か」という、言語を問わず文章を書く上で論理的に最も重要なところが、彼の頭の中でないがしろにされている
ということを端的に、如実に示しています。まさに、渡辺パコ氏が指摘しているとおりです。
次に、when が出てきた時点で、その後の部分が一つの文になっていなければならないのですが、彼は「メモリフリー」という、英語として正しいかどうか怪しい「名詞」を、Google で確認すらせずに、安易にもってきてしまいました。この怠慢にも、大きな副作用があります。読む人間が、
「この書き手はたぶんメモリを解放するさいに使えるといいたいのだろうが、なにせ英語がめちゃくちゃだから、メモリがすでに開放されているときといいたいのかもしれないな。どちらなのだろう?」
と、本来なら悩む必要のない、変なところで悩む可能性があるのです。
彼は、本当のところ、次のように書くべきだったということになります。
(2) メモリを解放するときはこのAPIが使える。
This API can be used when you wish to set the memory free.
しかし、上記の英文は、一発で書くにはそれなりの訓練が要ります。あまりにもきれいすぎる英語ですし、そもそも、受動態が含まれてしまっています。
このブログでは、以下が正解となります。
(3) メモリを解放するときはこのAPIが使える。
You can use this API to set the memory free.
現場で使える、同系統の例文を挙げておきます。
You can use Salesforce to manage your accounts.
Salesforceは、アカウントのマネジメントに使える。
You can hit Ctrl + D to copy the line above on an Excel spreadsheet.
Excelで Ctrl + D を叩くと上の行をコピーしてくれる。
ちなみに、某大手電機メーカに勤務されている、ソフトウェア開発のベテラン プロジェクトマネージャの方に、(1)の例文をお目にかけたところ、大笑いされておいででした。どうやら彼にとっても、この手の迷文は「あるある」だったようです。
根本原因は、私は、大学の入学試験の問題にある、と断言して はばかりません。このエンジニアの卒業した理系の国立大学は、一流であることは間違いないのですが、英語の二次試験に英作文が事実上出題されていないのです。
ビジネス英語は英作文能力が全てです。厳しい言い方ですが、彼はビジネスの現場では、英語ができるうちに入らないということです。
ビジネス英語のタブーを安室奈美恵の曲に学ぶ 1
ビジネスをアウトプットするときは、頭の中で常に 5W1H を考えておくことがとても重要です。これによって基本的な文法ミスを避けることができるばかりでなく、相手に伝えるべき情報が整理されるからです。
見た目ちょっと怪しくなってしまいますが、
『誰が、どうする、何を』
と、マントラのように唱えながら英文ライティングすると、効果的です。
この呪文は、『誰が、どうする、何を』が適当でもなんとか誤魔化せてしまう日本語の欠点を補完する効果があります。
私が知る限りでは、日本人、中国人のみが、英語のセンテンスに述語「どうする」「どうした」を入れるのを忘れてしまうことができるようです。
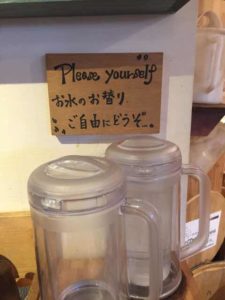
Please yourself…?
これは私の行きつけのカフェにおいてあるサインボードなのですが、これを書いた方を責めるつもりは毛頭ありません。カフェなら、これで、どうにかなります。外人は微苦笑は浮かべるでしょうが、
“Please help yourself.”
と言いたいのだろうな、とわかりますから、なんとなく。なにせ、水が目の前に置いてあるのだから。このブログでも重点的に取り上げていく、ビジュアルシンキングの強さです。
しかし、ビジネス英語においては、これは致命的です。どんなに発音がきれいでも、流暢に聞こえるしゃべりができても、こいつの英語はまるきり信用おけない、と、即座に断じられます。
私など、10年以上前の転職活動中、中国の ZXX という通信機器メーカーのプロジェクト・マネージャの募集要項に動詞なし英語を見つけたとき、その場で応募をやめました。中国語の全くできない私は苦戦必至、と悟らされたからです。
述語のない英語は、英語の構造の根本的な部分に関して無関心、かつ、各英単語の品詞に地の果てまで無頓着、と、自ら大声で宣言しているのと変わらないのです。つまり、欠けているのはセンスではなく、論理的な思考能力と、ほんのわずかな誠実さです。
小室哲哉氏が引退しましたね。英語に関心がある方の中には、ほっとした方も多いと思います。その作品の一つに安室奈美恵の “Can you cereblate?” (直訳「はたしてあなたに、どんちゃん騒ぎができますか?」)があります。
ビジネス英語のタブーが学べる安室奈美恵の曲 (YouTube)
安室が海外で歌ったら、聴衆がドン引きしたそうなんですが、それはそうでしょう。タイトルからして意味わからないし、歌詞にも、ぶっとんだ英語もどき満載だからです。
その中で、さすがの小室哲哉、きっちりといい仕事をしてくれています。
Let’s a party time tonight.
はい、述語「どうする」のない英語、きました。
「何も考えていないし考える気もない、語呂さえよければ全て良し」
なのだな、言い換えれば英語の正しさなんてどうでもいいと思っているのだな、と思い切りバレるわけです。
むろん、この文は、
Let`s have a party tonight.
としない限り意味が通じません。

Let’s Party!
一瞬、このチラシの作り手も同罪に見えますが、実はこちらのほうは正解です。実際にこの通りの標語のポスターが海外にあります。
party という、cry と同様に活用する動詞があるのです。ただ、party の p が大文字になってしまっているので、「本当はこの人これが動詞だって知らないんじゃないの?」という誤解をされやすいと思います。この動詞を知らなくても、ビジネス英語上で何のデメリットもないので、余談ですが。
(ほら、これも、ビジネス英語と英語の日常会話の共通点のなさを示しています。)
このタイプの赤っ恥をかくのを、ビジネス英語をアウトプットして行く上で、確実に避ける方法が、実はあります。下記のツールを使うのです。
ビジネス英語を書くのに必須のツール Grammarly
このツールは、入力した英語を文法的に精査し、誤りを指摘した上、文章の提案まで行ってくれる、至れり尽くせりの逸品です。Chrome にインストールできる拡張機能もあるのが嬉しい!ウエブフォームに記入する英語の文法、スペリングのミスも、その場で正してくれるのです。ぜひ、使ってみてください。
ビジネス英語のタブーを安室奈美恵の曲に学ぶ 2
前のお話では「どうした」が抜けていましたが、さすがに日本人の方でも、そのミスをされる方は少ないです。しかし、
『「何を」が抜けている』パターン
は、枚挙にいとまがありません。この記事で取り上げたエンジニアも、まさにこの好例でした。
「目的語欠落症」は、日本語の構造から、日本人がかかりやすい業病の一つです。逆に言うと、この問題にきちんとアドレスすると、英語をアウトプットする力がグッとアップします!

RETURN HERE. 必ずこの場所にご帰還ください。
この return は、スターウォーズ エピソード6「ジェダイの帰還」のサブタイトル Return of the Jedi と一緒の意味になります。
![スター・ウォーズ エピソード6 ジェダイの帰還 リミテッド・エディション [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ZWX2VQGFL._SL160_.jpg)
つまり、
「(客自身が)ここへ戻ってきなさい」
と客に命令しています。食器を戻せという意味には、絶対になりません。なぜなら、「何を」つまり、目的語がないからです。
それをいうなら、
Please return it here.
です。食器などもろもろ、という意味を込め、漠然とそれ it とモノを指す必要があります。
1. Luke Skywalker returns as a Jedi knight.
ルーク・スカイウォーカーがジェダイとして戻ってくる。
2. This function returns A as the pointer.
この関数はAをポインタとして返す。
1 の return は「何を」を必要としない自動詞、対して 2 のそれは、必要とする他動詞です。
問題は、しかし、このサインの作り手の念頭に、自動詞/他動詞の区別がなかったことではありません。むしろ、ビジネス英語の要諦(ようてい):
『誰が(お客様あなたが)、どうする(戻す)、何を(食器などを)』
がなかったことが最大の問題です。
以下は、日本国内にのみ はびこっている奇怪な英文?です。これも、典型的な「何を」つまり目的語欠落症です。
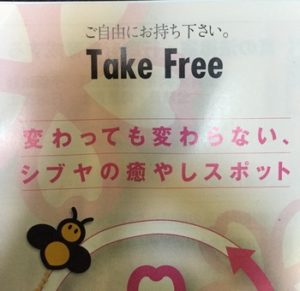
ご自由にお持ち下さい≠ Take Free
この表現、東京都内だけでも本当に頻繁に見かけますが、ネイティヴなら目が点です。
ロンドンに行くと、地下鉄の駅の構内に、新聞が無料で積んであるので重宝します。前回出張で行ったときはちょうど Brexit の議論沸騰(ふっとう)中で、現地の新聞を読み比べられて非常に興味深かったものです。ネイティヴは、無料の新聞を、例えばこのように表現します。
Free copy here.
この場合も、『誰が(あなたが)、どうする(とる)、何を(このパンフレットを)』が、書き手の念頭になかったことが、最大の敗因です。
「ご自由にお持ち下さい」と本気で言いたいのなら、正解は以下です。
“Please take one.”
「一部どうぞ。」
“Please yourself.”
を訂正した英文
“Please help yourself.”
「あなたが、助ける、自分自身を。」
でも、全く問題なく通じます。
同系統の例文を挙げておきます。
Let’s take that approach.
「我々はそのアプローチで行こう。」
安室奈美恵の名曲 “Can you cereblate?” (「あなたはどんちゃん騒ぎできますか?」)には、骨の髄まで学び倒す価値があります。(断っておきますが、安室奈美恵自身は、小室哲哉という災厄の被害者です。)
We will love long time
「私たちは未来になったら(……???を)愛することになるでしょう」
はい、目的語なし英語きました。しかも前回と同じ曲。ワクワクしますね。天下の小室哲哉は、期待を決して裏切らないのです。
これを文章として成立させるためには、
We will love each other for a long time.
でしょうが、それでも、ネイティヴがこの文章見たら、
「!?ってことは、いまはこの人たち愛し合ってないの?」
と疑問に思うと思います。この will は、
「よおし、いまはお互い大っ嫌いだけど、これからバリバリ愛し合うぜ~!だって愛って大切じゃん」
的な気合と捉えられても文句は言えません。
小室哲哉は「日本人に伝えようと思うと、文法的に正しくない英語を使わざるを得ない」的な発言をしているので、どんな素っ頓狂なことを考えてこの歌詞を考えたのか知りようがありませんが(笑)、たぶん、
We will keep loving each other for a long time.
「私たちは(誰が)愛し合い続けよう(どうする)お互いを(何を)」
って言いたかったんでしょうね。
時制を正確に使いこなすことも極めて重要です。このブログでも時制は丁寧に解説していきます。
象は鼻が長いをビジネス英語で言うと……?
ビジネス英語をアウトプットして行く上で、メインエンジンの役割を果たす第三文型の三大要素のどれが欠けてもいけません。ではなぜ、日本人は、やろうとしていないのについついやってしまうのでしょうか?
語順以外に、英訳の際に日本人を混乱させる日本語の要素に、助詞
「は」「が」
があります。
上で取り上げたエンジニアは、
「APIが使える」
という日本語を訳出する際、上記のワンステップを挟む手間を惜しみました、というよりは、たぶん、そんな考えなど露ほども持っていなかったのでしょう。「が」はすべからく主語を示すはずだという浅はかな考えに基づいて適当に英訳したおかげで、「何を」つまり目的語が欠落した、英語になっていない英語ができあがってしまったのです。
1. 「象は鼻が長い。」
この一文、英訳は、すぐに2パターン、思いつくことができます。
1)「象の鼻は長い。」
The trunk of an elephant is long.
2)「象は長い鼻を持っている。」
An elephant has a long trunk.
「XはYがZだ」は、日本人にとってすら厄介な代物です。日本語の段階で、この構文を思いついてしまったら、英訳の前に、必ずワンステップ、日本語で噛み砕いておくべきです。
2. 「この客はTAMが大きい。」
1) 「この客は、大きなTAMを持っている。」
This customer has a lot of TAM.
2) 「この客はTAMが豊かだ。」
This customer is rich in TAM.
3. 「彼はコミュニケーション能力が高い。」
→「彼はコミュニケーションがうまい。」
He is good at communication.
4. 「このソリューションはコスパが高い。」
→「これは費用対効果の高いソリューションである。」
This is a cost effective solution.
5. 「この競合は対応が早く、かつ、その対応は効果的である。」
→「この競合は素早く、かつ、効果的に反応する。」
This competitor responds quickly and effectively.
6. 「このシステムは冗長性が十分でない。」
→「このシステムは、十分な冗長性をもっていない。」
This system does not have enough redundancy.
これもあるあるなのですが、上でとりあげたくだんのエンジニア、そもそも、しっかりした日本語を文章を綴るのに難がありました。もし、彼が自らの欠点を自覚していたら、語学留学する前に、まずロジカルシンキングを学んで、思考を整理する術を身につけていたと思います。