ページ目次
「私は本当にサーブが苦手でね」
私はときどき、「こちらの質問に答えない」と妻に非難されます。私の父も、母によく同じことを言われていました(汗)。
はたしてこれ、私の血筋のせいでしょうか?
こんなやりとり、見たことないですか?
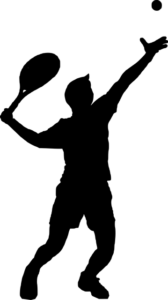
私はサーブが苦手でね
A. 「◯◯さん、テニスお好きなんですって?」
B. 「私は本当にサーブが苦手でね……」
よく見ると、Bさんは、Aさんの質問に、答えていませんね。私は、自分もテニス好きでかつサーブが苦手なこともあり、Bさんの気持ちはとても分かりますが、それにしても、これが業務なら、問題あるやりとりです。
営業部長 「◯◯さん、あの案件、クローズしたのかね?」
営業 「私は本当にあのお客様のご担当者が苦手でして……」
営業部長 「そんなことは聞いてない、クローズしたのかね、まだなのかね?」
以下は、実際に私が目にした、英語のやりとりです。エンジニアは日本人ではありません。
PM「今日の日本時間3時までにコードレビューまで終わりますか?」
エンジニア「テストシナリオのうち、3つで問題が起こっています。鋭意修正中です」
PM「いやだから、今日の3時までに終わりますか?』
エンジニア「◯◯さんが手伝ってくれています」
PM(キレ気味に)「あなたは私の質問に答えていない。3時までに終わるか?というのが私の質問です。YES、NOどちらです?」
エンジニア「3時に終わるかどうかはわかりませんが、頑張っています」
PM「……あんたの作っている機能は、今日のリリースには含めないよ。いまからコードレビュー、動作確認まで通ると思えないから」
↑こういうこと、身の回りで起こっていないでしょうか?
ちなみに、下記の本にも「質問に答えてくれなければ困るよ」というセリフが出てくるところから、この問題もまた、いろいろな職場で起こっている「あるある」だと思われます。
そしてこれもまた、英語がペラペラであっても全く解決しない、いや、むしろ英語がペラペラだと混乱がいや増す、コミュニケーションの根本的な問題です。
そのビジネス英語の質問、
日本語だったら、本当に答えられていますか?
私の知り合いのプロジェクトマネージャは、韓国のベンダをコントロールしています。彼は韓国語は学び始めたばかりで、最近、かろうじてハングルを読めるようになったそうです。その韓国のベンダの担当者は、日本語がカタコト、挨拶程度しかできません。
彼は私に、そのベンダの相手が、自分の質問に、絶対に一発で答えないと嘆いていました。
ハードウェアもソフトウェアも韓国製のシステムを、日本のお客様に導入するプロジェクトの、後半の話です。
彼はそのベンダに、
「日本で実施するシステム結合試験の完了予定日は、いつですか?」
と質問しました。そのベンダからの回答?は、
「当該ハードウェアは◯月◯日に韓国を発送予定です」
でした……。
仕方ないので、彼は、
「システム結合試験を×月×日に完了することに伴うリスクをあげてください」
と質問を変えたところ、入国審査にどの程度の時間が見込まれ、試験が全てうまくいったとしても、かなり厳しい、と、初めて直截的な回答がありました。
また、他の機会に、以下のような質問をしました。
「この機能の要件変更は、来年のサービスランチまでに対応可能でしょうか?」
その韓国ベンダから速攻で以下のような返信がありました。
「(来週納入予定の)ベータ版では、その要件変更の適用が困難です(原文ママ、翻訳エンジンを使った日本語訳)」
これらは一例にしかすぎず、毎回毎回すれ違いで、自分の質問へのダイレクトな回答が返ってこないことにうんざりしたその日本人のプロジェクトマネージャは、
「本当はやりたくないが、自分の質問の後に、『この質問には YES/NO で答えてください』と、回答オプションを指定するようになった」
といっていました。
さて、ビジネス英語を習得し、英語によるコミュニケーション能力を伸ばしたい皆さんに、考えていただきたいです。
上記は、日本人のプロジェクトマネージャが韓国語に堪能だったり、韓国のベンダが日本語を流暢に話せれば、解決する問題でしょうか?
そして、この問題が解決しないのに、お互いの言語を学ぶことに、どの程度のメリットがあるでしょうか?
英語で長くしゃべりたくなければ……
「手短に」が15分
私の知り合いの、ある大手電機メーカーに勤務するプロジェクトマネージャJ氏が、インドでオフショアをやっていたときのエピソードです。
インドのベンダのコントロールをやっていた彼は、進捗が悪いことを心配し、ベンダに理由を尋ねました。すると、その大手電機メーカーのソフトウェア開発チームの準備したAPIに問題があるといいます。ベンダ側のプロジェクトマネージャと本来問題を協議するところ、そのPMがその日は病欠だったため、インド人のエンジニアのI氏と直接話すことになりました。
インド人のI氏はもちろん、日本人のJ氏も、全く支障なく英語を操ります。
J「それは申し訳ないことをしたかもしれません。うちの開発チームのマネージャにエスカレートするから、問題点を短くまとめてくださいませんか?」
I「Jさん、問題の一つは、コードのクオリティです。昨日、御社の開発チームの◯◯さんと、30分も話しました。Jさん、ご記憶にあるかもしれませんが、私は、◯◯さんと話す前に、APIに関する問題点を一つ、イシューリストに挙げています。Jさん、この問題の技術的背景を説明させていただきますと、もともとの仕様では………」
J氏が開発をオフショアしているシステムは、コンポーネントがいくつもある大規模なもので、J氏は三つのベンダを同時にコントロールしていました。イシューリストに最近何が登録されたかなど、詳細を把握しきれるものではありません。言い方は悪いですが、J氏は、
「そんな細かいことは私の知ったこっちゃない」
と思ったはずです。
エンジニアI氏は、彼のいう問題点四つをカバーするため、たっぷり15分間もとうとうと技術の話をしましたが、J氏はついに、何を自社の開発チームにエスカレートすればいいのか、把握できずに終わりました。
仕方なくJ氏は、エスカレーションの内容を、翌日出社したベンダ側のプロジェクトマネージャにまとめてもらいました。その報告のメールは、極力短くとJ氏が繰り返し要求したせいもあって、たった5行だったそうです。J氏はこれを直ちに自社の開発マネージャに転送し、問題は速やかに解決しました。
さて、この問題は、J氏が流暢にヒンディー語をしゃべれたとして、解決できたでしょうか?
私自身も何度か、技術者が、報告や質問への回答の冒頭に、
「この問題について誰々さんと誰々さんと話し合いました」
と前置きするのを経験しています。はっきりいって、蛇足です。そんな詳細は、訊かれたら初めて付け加えれば良いのです。最初の段階では割愛すべき情報です。
ある問題が生じたら、マネージャが即座に把握しなければならないのは、以下です:
(1) その問題は解決済みか?
(2) その問題は、最終的に、誰にどんな影響を与える(与えた)か?どの影響の規模は?
(3) 未解決なら、その問題の解決案/ワークアラウンドは?
(4) 解決案があるのなら、いつまでに解決できるのか?
I氏の念頭に、このスキームが存在しなかったのは明らかです。要するに、相手の立場に全く立っていなかったのです。
ビジネス英語の質問に回答するとき
知らないと質問者に迷惑がかかる原則
なぜ質問に答えられないのか?
今までとりあげてきた、「質問に答えない人」は、善意からそうしたのだと思います。
韓国ベンダの担当者は、日本で結合試験を終えるタイミングをコミットするのがはばかられて、予定としてより確実な、韓国からハードウェアを発送する予定日を回答したのかもしれません。また、技術者のリソースがいっぱいいっぱいなので、機能変更は、現時点では対応不能と予防線を張ったのでしょう。
インド人のエンジニアI氏は、できるだけ詳細な情報を与えるのが親切だと信じて、一から十まで語って、状況を正確に把握してもらおうとしたのだと思います。
(余談ですが、どうやら、たくさんしゃべることは、インド人にとって、サービス精神から出てくる行為のようです。
私はインドに渡航した時は、決して周囲のインド人に道を尋ねません。彼らは善意から、たとえ本当は道を知らなくても、でっちあげてでも、道を教えてくれようとするからです(汗)。)
彼らに足りなかったのは、
「相手のニーズ demand に的確に応えよう」
という意識です。
彼らは、たとえ親切心からにせよ、相手の聞きたいことではなくて、受けた質問から連想した、自分たちがしゃべりたいことをしゃべってしまったのです。その結果、無駄なやり取りで、相手と自分の時間を無駄にしてしまっています。時は金なり、のビジネスの世界では、時間を無駄にすることは、もちろん、よくないことです。
誰がコミュニケートするのか?
電車の中や道端で、声に出して自分にしかわからないことをつぶやいている人を見かけますが、コミュニケーションはそこにはありません。相手の本当に理解したいことをしっかり考えずに、ひとりよがりな言葉を並べて回答する人もまた、実は、寸分(すんぶん)変わらないことをやっているのです。
ドラッカーは、著書「マネジメント」のコミュニケーションに関する章で、
「周囲に誰も聞く者がいないところで森の木が倒れたら、そこに音はあるか?」
という禅問答を取り上げた後、「正解は『ない』である」とした上で、以下のように述べています。
First, it means that it is the recipient who communicates. The so-called communicator, the person who emits the communication, does not communicate. He utters. Unless there is someone who hears, there is no communication. There is only noise. The communicator speaks or writes or sings—but he does not communicate. Indeed, he cannot communicate.
Drucker, Peter F.. Management: Tasks, Responsibilities, Practices
「第一に、これは、受信者こそがコミュニケートするのだ、ということを意味する。いわゆるコミュニケーター、コミュニケーションを発信する人間は、コミュニケートしないのである。彼は言葉を発するだけだ。誰かその言葉を聞きとる誰かが存在しない限り、コミュニケーションはそこにはない。雑音があるきりである。コミュニケーターは話したり、書いたり、歌ったりするーーしかし、彼はコミュニケートしない。そう、彼はコミュニケートできないのだ。」
質問に答える場面でコミュニケートするのは、質問者であって、回答者ではないのです。これをわきまえていない回答者は、すれ違いを生んでしまいます。
ビジネス英語で質疑応答するとき、必ず準備すべきこと
そして、だからこそ、質問されたら、その質問に確実かつ端的に答えるのは、見かけほど簡単ではありません。相手の理解したいことを正確に把握するのは易しくないですし、別に回答を誤魔化したいわけでもないのに、人間は、訊かれてもいないことを先回りして答えたり、細かいところから説き起こしたりしてしまいします。
私もときどきこれをやってしまうので、質問されたときは、
いま何を訊かれたのか?
YES/NO なのか?ファクトなのか?理由なのか?それとも、私の案か?
と、一度質問を腹に落としこんでから、できるだけダイレクトに、アンサーファーストで回答しようとします。
この作業を事前に行うことには、3つの良い点があります:
- 相手が日本語がしゃべれない場合でも、もちろん、この作業自体に英語の知識は全く不要です。純粋なロジカルシンキングのプロセスですから。
- アンサー自体の内容は短いことがほとんどです。というよりも、質問者のために、回答者は、これを極力短くしなければなりません。したがって、長い文章に比べて、この一手間をかけることで、英訳はぐっと容易になります。
- 相手の質問により的確にアドレスすることができ、伝わりやすくなります。
枝葉だらけの的外れな回答を美しい表現の英語で流暢にしゃべりまくったとしても、相手を混乱させるだけです。コミュニケーションを成立させられません。ビジネス英語は、語学ではないのです。
ビジネス英語で受けてはいけない3つの質問
ビジネス英語では、
巨人の正体をいきなりあかしてしまえ!
ベストセラー漫画「進撃の巨人」シリーズを読み始め、いいように巨人たちに蹂躙される人類の行く末にハラハラしている人に、
「実はこの巨人の正体はね……」
とネタばらしをしたら、まず間違いなく嫌われるでしょう。
映画や漫画、小説は、起承転結で書かれています。推理小説などは、いわゆる倒叙モノという犯人が最初に明かされるタイプを別として、最後のページまで犯人がわからないのが最高だったりします。
ところが、業務のコミュニケーション、特にビジネス英語では、この起承転結式のメッセージは、絶対的なタブーです。
以前、ある若い日本人の技術者の部下から重要な問題に関する報告を受けたことがあります。彼は、問題の発端から始まってえんえんと詳細、つまり枝葉末節を語っているので、次のミーティングまで時間がなかった私は、途中で、
「で、結論は何ですか?」
とさえぎらざるをえませんでした。
私は「最後まで聞いてください!」と彼に逆ギレされました(笑)。
職場は映画館ではありません。
『ルーク・スカイウォーカーは、旅に出、数々の艱難辛苦(かんなんしんく)を経て、一人前のジェダイになった』
これだけのメッセージを伝えるのに、スター・ウォーズ三部作6時間を費やすのは、あまりにもったいないです。
また、上記の一文のみをサクッと翻訳するのと、三部作の脚本をすべて翻訳するのと、どちらが発信者にとって手間でしょうか?
上記の日本人の技術者も、彼がとうとうと述べていたことを全部英訳するのは、骨が折れたはずです。
ビジネス英語では受けてはいけない質問 その1
ビジネス英語でやりとりしていて、決して受けてはいけない質問が3つあります。
その1は、ここまでの議論から、言うまでもなく、以下です。
「それで、私の質問に対する答はなんですか?」
“Would you answer my question?”
ビジネス英語では受けてはいけない質問 その2
受けてはいけない質問2は、以下です。
「割り込んで申し訳ないけど、要点はなんですか?」
“I am sorry for interrupting you, but, what is your point?”
結論ファースト Conclusions first は、相手を尊重したメッセージングの基本の基です。
例えばメールのタイトルには、メッセージの結論を簡潔にまとまっているべきです。ことに、そのメールがなんらかのアクションを相手に要求する場合、そのアクションがタイトルを見て、メールを開けて読まなくても、一瞥で理解できなければなりません。
メールであっても、コミュニケートするのが受信者だという原理は、むろん当てはまります。
メールを送った相手が、忙しいマネージャだった場合のことを考えましょう。
1日に100通以上のメールが、その受信トレイに入ってきています。受信トレイがいっぱいの状況で、件名が、
「◯◯案件について」
というメールが、新たに飛びこんできました。
件名が漠然としているので、すぐには開けません。ところが、後になってメールを開けて、その長いボディを読み込んでみると、それはエスカレーションで、そのマネージャに重要で緊急の判断を求めていることがわかりました。
……最悪ですね。
これが、たとえば、
「【緊急:◯◯案件】発注額減についてご判断をお願いいたします」
となっており、メールを開けると、以下のようになっていたら、マネージャはすぐに最も妥当なアクションが起こせるでしょう。
「△△部長、
お客様の予算額が減少し、先方が払える発注額の上限が300万となってしまいました。つきましては、以下の松竹梅のうち、いずれを選択すべきか、ご判断をお願いできますでしょうか。
松:お客様の別の部署からの××案件の受注額を増額していただいての、本案件の受注
竹:利益が15万程度になることを覚悟して、本件の受注
梅:本件を受注しない
お客様の予算額が減少した理由は……。
松竹梅各プランのメリット、デメリットは……。」
余談ですが、大木 豊成氏は、下記の自著の中で、
「〜です。お疲れ様です。」
という挨拶文をメールの冒頭に挿入するのは、メイクセンスしないと指摘しています。
私も、意味のない冗長な情報を読ませることで、受信者の時間を奪うべきではないと思います。
メールのタイトルに打ちたいことを好きなように打って、この原則に適合しているかどうか確かめもせずに送信ボタンを押す人は、相手の時間を尊重しない人、といえるでしょう。
ビジネス英語では受けてはいけない質問 その3
受けてはいけない質問3は、以下です。
「割り込んで申し訳ない。それで、あなたの質問とはなんですか?」
“I am sorry for interrupting you. So, what is your question?”
以前私は、CXOの一人である上長の席へいって、
「相談がございます」
と切り出したことがあります. その後, 私が, その相談の背景から説明し始めたため, 人一倍 straightforward なコミュニケーションを好むその上長は、すぐに
「それで、相談とはなんですか?」
とさえぎってきました。
私は恥入りました。この質問は、相談を持ちかけた側が受けてはいけない質問です。この質問を受けたら、その相談にさいして、準備が不足していると指摘されたに等しいのです。
私は慌てて相談内容を直接伝え、上長もすぐに簡潔な答を返してきました。
これをやってしまったのは私だけではないようです。
これらの質問が本当に指摘していること
鋭い方は、これら3つの質問が、事実上、同一であることに感づかれたはずです。
これらの質問はいずれも、
発話者が遠回りし始めた、つまり発話者が受信者の時間を十分に尊重していない
ことを、指摘しているのです。
これらの質問を受けないためには、コミュニケーションの発信者は、受信者の立場に立って、
「ようするに In summery 自分は何を言いたい/聞きたいのか?」
ということを、あらかじめ日本語の思考の段階で、整理しておく必要があります。
重要な蛇足
上に書き連ねてきたこととある意味矛盾しますが、ビジネス英語で質問を受けたとき、the straightforward answer の前に一つだけ、付け加えてよいセンテンスがあります。
それは、日本人の発想にはあまりない言葉です。
Thank you for your question.
これは、極端な話、毎回定型文として返しても支障はないくらいです。私などは、これを口にしている間に、何を答えようか必死に準備します(笑)。
以前カルフォルニアで研修を受けたとき、ブリテン人の同僚が、
“This might be a stupid question, but…”
「これってバカみたいな質問かもしれないけど……」
と前置きして質問したのに対して、インストラクターが、
「とんでもない、質問ありがとう」
と受け答えていたのが印象的でした。
欧米の文化では、よい質問をする人間は、高く評価されるのです。

![ドラッカー名著集14 マネジメント[中]―課題、責任、実践](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41zNvzEEJaL._SL160_.jpg)

